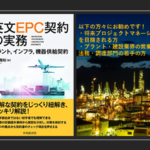英文契約でindemnify and hold harmlessとbe liable
以下の条文は、indemnity条項、またはhold harmless条項と言われている条文です
これは、売買契約や請負契約等において、売主の製品や仕事が原因で第三者が損害を被った場合に、売主が買主を免責し、買主に迷惑が掛からないようにするために定められる条文です。
The Seller shall indemnify and hold harmless the Purchaser from and against all damages, claims, losses, expenses, including without limitation, reasonable attorney’s fees, made against the Purchaser in respect of the death, human bodily injury or damage to any property arising out of the Seller’s performance of the obligation hereunder and due to the Seller’s negligence.
訳:売主は本契約に基づく売主の義務の履行から生じた生命、身体、その他の財産への侵害で、かつ、売主の過失に基づくものに関して買主に対して課せられた、合理的な弁護士費用を含むがこれに限らない全ての損害賠償額、損害賠償請求支払額、損失額、諸費用について、買主を補償し、免責する。
このindemnity条項は、その構文が分かりにくいことから、英文契約の中でも有名な条項だと言えると思います。
indemnity条項についての疑問
企業法務として働いてしばらくしたころ、私はこのindemnity条項について、ある疑問を抱きました。
それは、このindemnity条項を、「be liable for」を使って書いてはいけないのだろうか?というものです。
具体的には、上の条文を次のように書くと何か不都合があるのでしょうか?
The Seller shall indemnify and hold harmless be liable to the Purchaser from and against for all damages, claims, losses, expenses, including without limitation, reasonable attorney’s fees, made against the Purchaser in respect of the death, human bodily injury or damage to any property arising out of the Seller’s performance of the obligation hereunder and due to the Seller’s negligence.
この条文の意味は、「売主は、本契約に基づく売主の義務の履行から生じた生命、身体、その他の財産への侵害で、かつ、売主の過失に基づくものに関して買主に対して課せられた、合理的な弁護士費用を含むがこれに限らない全ての損害賠償額、損害賠償請求支払額、損失額、諸費用について責任を負う」となります。
実質的には、「とにかく買主が被った損害等について売主が責任を負う」という意味になるので、こちらでも良いように思ったのです。
そして、be liable forを使って書いたほうがindemnify and hold harmless…を使って書くよりも、表現が簡単で、ずっと書きやすいように感じました。
実際、他社から送付されてきた契約書や、英文契約の参考書における第三者が被った損害についての条項として、indemnify条項ではなくbe liable forを使って書かれているものも見たこともありました。
この点、様々な英文契約に関する参考書を調べてみたのですが、「第三者の損害に関してはbe liable forで書いてはダメで、必ずindemnify and hold harmlessを用いて書かなければならない」ということを言っているものはありませんでした。
ということは、be liable forを使って書いてもよいのだろうか・・・?
しかし、実態としては、第三者の損害についての条項は、indemnify and hold harmlessを使って定めるのが通常で、また、実務上そのように定められている数も、be liable forを使って書くよりも圧倒的に多いと言えると思います。
なぜindemnify and hold harmlessと書くのか?
上記にも書いたとおり、be liable forを使って定めていけないのか否かははっきりとはわからなかったのですが、どうして、indemnify and hold harmless…なんて難しい表現が使われているのかについて、自分なりに考えてみました。
まず、売買契約や請負契約において、対象となる製品や仕事が原因で第三者に損害が生じた場合、その第三者は誰に直接損害賠償を請求するのが普通なのか?と考えると、それは買主・注文者に対してでしょう。
なぜなら、第三者と売主・請負人との間には、契約関係がないので、第三者は契約責任を売主・請負人に対して問うことができないからです。
そのため、第三者が売主・請負人に対して直接請求しようと思ったら、不法行為責任に基づくことになります。
不法行為責任に基づく請求は、立証の観点から、被害者である第三者に不利です。
この点、日本では製造物責任法(PL法)があります。
このPL法によれば、損害を受けた第三者は、立証の観点で不利益を被ることなく、売主・請負人に対して損害賠償を請求することができます。
そしてこのPL法と同趣旨の法律は、米国にもありますし、その他の海外の国々にもあることでしょう。
よって、損害を被った第三者は、理論的には、直接、売主・請負人に対して損害賠償を請求できる条件が整っているはずだと言えます。
しかし、それでも、第三者は、自分が直接取引したわけではない売主・請負人に対して請求するよりも、買主・注文者に請求しやすいのだろうと思います。
売主から直接問題となっている製品を買って使用していた買主、請負人に仕事をさせていた注文者の方が、第三者からみて、請求の対象者としてわかりやすい、という実態があるのだろうと思います。
そうすると、買主・注文者としては、自分が第三者から損害賠償を請求された場合には、原因を作った売主・請負人に対応してもらうこと、そして、買主が一旦第三者に支払った賠償額分を支払ってもらう必要が生じます。
よって、条文としても、単に「売主は買主に対して責任を負う」という定めではなく、より実態に合った「売主は買主を免責し、補償する」という定めになったのではないかと思います(「責任を負う」という表現よりも「免責し、補償する」の方がより具体的な表現)。
確かに、「be liable for」よりも、「indemnify and hold harmless」の方が、第三者から買主が請求されている状態から売主が買主を救い出すニュアンスが出ているように思えますよね。
というわけで、今回のまとめです。
- 第三者の損害についての条文として、indemnify and hold harmless…ではなく、be liable forで書いていけないのかどうかは英文契約関係の書籍を色々読んだがはっきりとはわからなかった。
- 実態としては、be liable forを使って書かれている条文も見たことはあるが、indemnify and hold harmlessを使って定めているものの方が圧倒的に数は多い。
- 損害を被った第三者は、買主・注文者に対して損害賠償を請求してくるという実態があることを考えると、be liable forよりもindemnify and hold harmlessの方がより実態に合致した条文のように思える(私見です)。
-
目次 第1回 義務 第10回 ~に関する 第19回 知らせる 第2回 権利 第11回 ~の場合 第20回 責任 第3回 禁止 第12回 ~の範囲で、~である限り 第21回 違反する 第4回 ~に定められている、~に記載されている 第13回 契約を締結する 第22回 償還する
第5回 ~に定められている、~に記載されている (補足) 第14回 契約締結日と契約発効日 第23回 予定された損害賠償額(リキダメ、LD) 第6回 ~に従って 第15回 事前の文書による合意 第24回 故意・重過失 第7回 ~に関わらず 第16回 ~を含むが、これに限らない 第25回 救済 第8回 ~でない限り、~を除いて 第17回 費用の負担 第26回 差止 第9回 provide 第18回 努力する義務 第27回 otherwise 第28回 契約の終了
第38回 権利を侵害する 第48回 遅延利息 第29回 何かを相手に渡す、与える
第39回 保証する 第49回 重大な違反 第30回 due
第40回 品質を保証する 第50回 ex-が付く表現 第31回 瑕疵が発見された場合の対応 第41回 補償・品質保証 第51回 添付資料 第32回 ~を被る 第42回 排他的な 第52回 連帯責任 第33回 ~を履行する 第43回 第53回 ~を代理して 第34回 果たす、満たす、達成する 第44回 第54回 下記の・上記の 第35回 累積責任 第45回 瑕疵がない、仕様書に合致している 第55回 強制執行力 第36回 逸失利益免責条項で使われる様々な損害を表す表現 第46回 証明責任 第56回 in no event 第37回 補償・免責 第47回 indemnifyとliableの違い 第57回 for the avoidance of 第58回 無効な 第68回 representations and warranties 第59回 whereについて 第69回 material adverse effect 第60回 in which event, in which case 第70回 to the knowledge of 第61回 株主総会関係 第71回 GAAP 第62回 取締役・取締役会関係 第72回 covenants 第63回 indemnifyとdefendの違い 第64回 Notwithstandingと責任制限条項 第65回 M&Aの全体の流れ 第66回 conditions precedent 第67回 adjustment
【私が勉強した参考書】