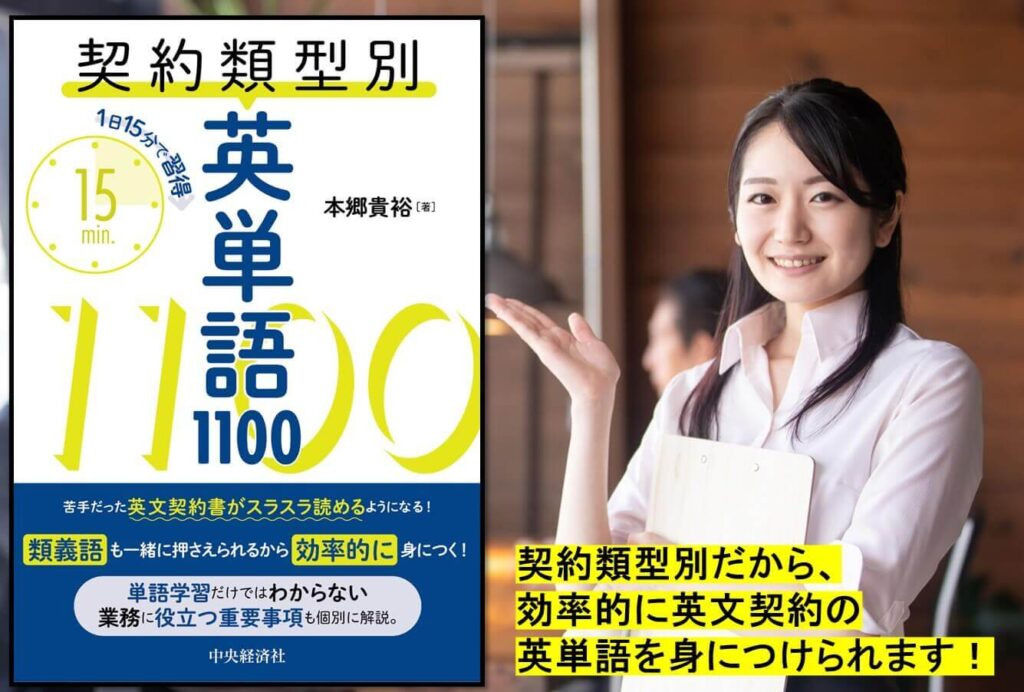責任上限条項にNotwithstanding anything~とついているのはなぜ?

責任上限条項(limitation of liability=LOL)に、次のような文言が付いていることが多いと思いませんか?
Notwithstanding anything provided herein
(本契約に定められているいかなる文言にもかかわらず)
これには、たまたまではなく、はっきりとした理由があります。
この記事では、この点について、詳しく解説します。
問題
売買契約に、次のような条文が定められていたとします。
第Y条:「売主は、第X条に違反した場合、買主に対し、一切の損害を賠償する責任を負う。」
第Z条:「本契約に関して各当事者が相手方当事者に対して負う責任は、契約金額の100%を超えない。」
ここで、問題です。
今、売主が、第X条に違反し、それによって買主が契約金額の100%を超える金額の損害を被った場合には、売主の責任は契約金額の100%までで良いことになるでしょうか?
優先順位
この点、第Z条が適用されるので、売主の責任は当然に契約金額の100%に制限されると考える人もいるかもしれません。
私も、売主の立場なら、そう考えたいところです。
しかし、上記のY条とZ条の記載からは、必ずそう解釈されるとは言い切れません。
というのも、Y条とZ条のどちらが優先して適用されるのかがはっきりしないからです。
そのため、Y条がZ条に優先すると解釈されることもありえるのです。
つまり、次のような解釈も成り立ちます。
「X条以外の条文に違反した場合には、Z条が適用され、売主の損害賠償責任は契約金額の100%に制限される。しかし、X条違反の場合には、Y条に特別に「一切の損害を賠償する責任を負う」と定められているので、Z条は適用されず、売主は一切の損害を賠償しなければならなくなると解釈するべきである。」
対策
もちろん、売主としては、Y条がZ条に優先して適用されては困ります。
そこで、対策として、冒頭で述べた文言を、Z条=責任上限条項に以下のように付けておくことがよくなされるのです。
Article Z (Limitation of Liability)
Notwithstanding anything provided herein, the Seller’s aggregate liability to the Purchaser in connection with this Contract, whether in contract, tort, or otherwise, shall not exceed the amount of 100% of the Contract Price.
(本契約に定められているいかなる条文にもかかわらず、本契約に関し、売主が買主に対して負う累積責任は、契約上のものであれ、不法行為上のものであれ、契約金額の100%を超えない。)
このようにしておけば、Z条がY条よりも優先することが明確になります。
つまり、売主がX条に違反した場合でも、Z条によって、売主は契約金額の100%までしか責任を負わなくてよいことになるのです。
結論
以上から、責任上限条項には、Notwithstanding anything provided hereinという文言がついていることがよくあるのは、たまたまではなく、ちゃんとした理由があったのです。
責任上限条項をチェックする際は、上記の点に気を付けるようにしましょう。