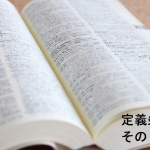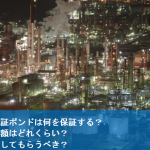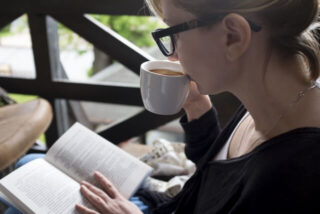英文契約書における一般条項の解説

一般条項とは?
これは、契約業務に携わっている人には簡単すぎる質問ですよね?
しかし、契約業務に携わったばかりの人は、「一般条項」という言葉を聞いても、何のことを指しているのかわからなかったりするのではないでしょうか?
私も、会社に入るまで法律の勉強をそれなりにまじめにしていたにも関わらず、この「一般条項」という言葉を学生のうちに聞いたことはなく、会社の企業法務部に配属されてから初めて聞きました。
では、「一般条項」とは、一体何を指すのでしょうか?
これは、「契約書の中に、一般的に定められることが多い条項」といった意味です。
あらゆる契約書に、常に定められているわけではありません。
というのも、契約書は人間が作るものなので、ときどき一般条項の中のいくつかを入れ忘れたり、あるいは、今回はこの一般条項は入れなくてもよいか、と考えて、あえて契約書の中に定めなかったりするからです。
しかし、原則としては、あらゆる契約書の中に一般条項をきちんと定める方が望ましいと言えます。
一般条項はあってもなくてもよい条文なのか?
一般条項は、契約実務の中では、いつも似たような、というよりも、ほぼ同じ内容で契約書中に当然のように定められているので、そのチェックも簡単に行われることが多いと思います。
そのためか「一般条項」=「さほど注意してチェックしなくても良い条文」というイメージが持たれてしまいがちです。
その結果、「どーせ今回もいつもと同じことが書いてあるんでしょ?」という気持ちでさらっと確認されるだけの条文になっていることが多いと思います。
確かに、一般条項の多くは、いつもほぼ同じ内容で定められています。
簡単なチェックで済ませることができる条文が多いといってもよいかもしれません。
しかし、だからといって、「一般条項がどうでもよい条文である」という結論にはなりません。
とうのも、一般条項は、契約書の中に定められることがあまりに多かったことから、「これらの条項は、一般的に契約書に定めることにしよう」と多くの人たちが考えるようになり、その結果、いつしか、「一般条項」と命名されるに至ったものだと考えられるからです。
つまり、一般条項は、「あまりにそれが重要な内容を含んでいたためにあらゆる契約書に定められ続けた」という歴史的な経緯があるのです。
「契約書の中に定められているのがほぼ当たり前になるほどの条文である」ということは、実は一般条項は、「どの契約書にも定められるべき重要な条文である」ということなのです。
したがって、一般条項は、あくまで、「重要な内容を含む条文であり、だからこそ、どの契約書にも定められることが当たり前になったのだ」と理解していただきたいと思います。
一般条項をそのように位置付けたうえで、その内容、チェックするべきポイントを理解することが大切です。
それができれば、結果として、一般条項のチェックというのは、その他の条文と比べて、簡単に・迅速にできるようになります。
くどいようですが、決して、「いつも同じことが書いてあるから、一般条項のチェックはスルーしてよい(見なくてもよい)」ということではないのです。
契約書における一般条項の種類にはどんなものがあるのか?
契約書の主な一般条項の種類は、概ね以下のようなものがあります。
リンクをクリックすると、詳しい解説のページに行くことができます。
【一般条項の解説の目次】
|
総論
|
完全合意条項・修正条項
契約に関する事項については、契約書にすべて定められている旨を定める条項 (正確には、口頭証拠排除の準則が適用されやすくするための条文) および 契約書を修正・変更するための条件を定める条項
|
|
契約書中で使われる文言の意味を定義する条項
|
無効な部分の分離条項
契約書中のある部分が無効と判断された場合、残りの部分は有効である旨を定める条項
|
| 定義条項その② 定義条項の注意点
契約書中で使われる文言の意味を定義する条項
|
権利放棄条項
ある事項について権利を保持する当事者がその権利を行使しなかった場合でも、その権利自体を放棄したものと解釈されないことを定める条項
|
| 準拠法
契約条文を解釈する際に適用する法律を特定するための条項
|
見出し条項
契約書中の条文のタイトルには法廷拘束力はなく、条文の解釈に何ら影響を及ぼすものではない旨を定める条文
|
| 紛争解決条項
契約に関する紛争を解決するための方法を定める条項
|
一般条項がわかるようになると得られるメリット
|
| 通知条項
契約に関して必要となる通知の宛先を定める条項
|
全ての一般条項を必ず定めないといけないのか?
|
| 契約期間
契約の有効期間を定める条項
|
|
| 権利義務の譲渡制限
契約上の権利義務を第三者に譲渡することを制限する条文
|
【私が勉強した参考書】