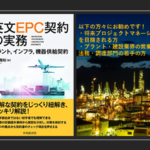EPC契約におけるコストプラスフィー契約の注意点を押さえよう!

コストプラスフィー
コストプラスフィー契約とは、契約締結時において、オーナーがコントラクターに対して支払う総額が固定されず、コントラクターが仕事を完成するまでに実際に生じた費用に、予め合意された割合分を足した金額をオーナーがコントラクターに対して支払うという方法をとる契約のことをいいます。
もっとも、全ての仕事についてコストプラスフィーとするよりも、一部の仕事だけコストプラスフィーとすることが多いかもしれません。
なぜなら、仕事の中には、予め総額を決めやすいものと、決めにくいものがあり、前者についてまでコストプラスフィーとする必要はないからです。
つまり、ある一定の仕事については固定価格(Fixed Price)とし、残りの仕事をコストプラスフィーとするのです。
コストプラスフィーの例文
そのような仕組みとなる例文を見てみましょう。
- Fixed Price
Owner and EPC Contractor agree that EPC Contractor shall be paid for all Engineering Services and [ ] for a fixed price, as provided in Exhibit X.
- Cost plus Fee
Owner and EPC Contractor agree that EPC Contractor shall be paid in accordance with Exhibit Y for all Construction Work, excluding Engineering Services and [ ] included in Exhibit X.
まず、上記の1つ目の例文は、Fixed Price部分を定める条文です。ここでは、Engineering Serviceと、添付資料Xに定められる仕事([]内に具体的に仕事の内容を記載します)がFixed Priceとなることを定めています。
そして、2つ目の例文は、Engineering Serviceと添付資料Xに定められている仕事を除くConstruction Workを添付資料Yに従って支払うことを定めています。このConstruction Workがコストプラスフィーで支払われる仕事となるのですが、その点は以下の添付資料Yに具体的に定めています。
Exhibit Y
1. Construction Costs/Pass-Through + 4.5%
For the performance of the Work, EPC Contractor shall be paid the Cost of the Construction Work, plus a fee of four and one half percent (4.5%) of the Cost of the Construction Work (the “Contractor’s Fee”).
2. As used herein, the term “Cost of the Construction Work” shall mean the following actual costs necessarily and reasonably incurred by EPC Contractor in the performance of the Work.
(a) [具体的に仕事を記載]
(b) [具体的に仕事を記載]
(c) [具体的に仕事を記載]
・
・
・
3. Owner acknowledges that EPC Contractor’s budget for the Cost of Construction Work, as set forth in Exhibit Z, is merely an estimate and subject to change.
添付資料Yの1つめの例文では、コストに載せるフィーを、Construction Workにかかるコストの4.5%と定めています。
次に、2つ目の例文では、コストプラスフィーの「コスト」に当たる部分であるConstruction Workのコストとは具体的に何か?を定義しています。ここでは、(a)~(c)に列挙する仕事をConstruction Workとしています。これが、実際に生じた費用を支払ってもらえることになる条文です。
さらに、3つ目の例文では、添付資料Zには、Construction Workにかかる費用の予定を記載することにしています。ここに記載された金額は、あくまで予定に過ぎず、これを越えても、コストプラスフィーとしてコントラクターはオーナーから支払いを受けることができます。ただ、この予定よりも増えた場合、オーナーは「なぜ増えたのか?」を説明するようにコントラクターに求めてくることになるでしょう。その理由次第では、オーナーが支払を拒むこともありえます。
なお、この他に、コントラクターには、コストプラスフィーが適用されるコスト部分の証拠記録の保管とオーナーへの開示義務が定められるのが通常です。
これは、コントラクターが実際にかかったコスト以上の金額を請求していないか、または、本来妥当とされる金額以上のコストがかかっていないかをオーナーが確認できるようにするためです。
コストプラスフィーの注意点
ここで注意したいのが、添付資料Yの2つ目の例文の「以下の仕事のためにコントラクターに生じる必要かつ合理的な金額」を、オーナーが支払うべきthe Cost of the Construction Workとしている点です。
記録次第では、「コントラクターに生じる必要かつ合理的な金額」ではない、となる可能性もあるのです。その場合、コストプラスフィーに関する条文の適用を受けない=支払い対象外=コントラクターが負担することになる、という結果になり得ます。
以上からわかるように、コストプラスフィーは、「なんでもかんでも、コントラクターに生じた費用を全部オーナーが支払ってくれる方法」ではありません。
「必要かつ合理的な費用」が支払われるものです。
コントラクターは、この点を忘れず、適切に仕事を遂行し、下請などからは相見積もりをとり、なぜその金額になったのか、それが合理的といえるのかをしっかり説明できるようにしましょう。
EPC契約のポイントの目次
『英文EPC契約の実務』は、海外で翻訳出版されることになりました!
また、お陰様で出版から6度の増刷となっております。
この本は、
・重要事項についての英語の例文が多数掲載!
・難解な英文には、どこが主語でどこが動詞なのかなどがわかるように構造図がある!
・もちろん、解説もこのブログの記事よりも詳しい!
・EPCコントラクターが最も避けたい「コストオーバーランの原因と対策」について、日系企業が落ちいた事例を用いて解説!
・英文契約書の基本的な表現と型も併せて身につけることができる!
ぜひ、以下でEPC契約をマスターしましょう!
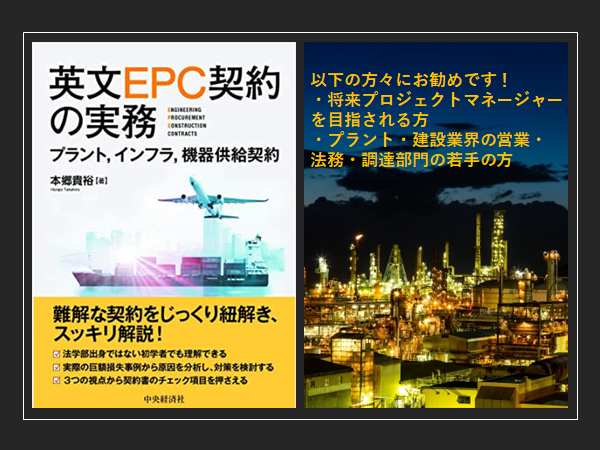
ちなみに、海外案件に携わり始める方々に向けた以下の本も好評発売中です!
『はじめてでも読みこなせる英文契約書』(税込みで2,640円)
海外との契約業務に関わることになった新入社員や若手社員の方々。法学部出身でなくても、法務部でなくてもわかると好評で、これまで既に10度の増刷となっており、2024年1月時点で発行部数が1万2000部に到達いたしました!
英文契約の参考書よりも潜在的な読者数が圧倒的に多い一般的な英語の参考書ですら、発行部数が5000部に到達しないケースがほとんどだそうです。その中で1万部を達成できたのは、ご購入いただいた方々が、職場の後輩やお知り合いの方々に本書をおススメしていただけているからだと思います。
中には、職場で英文契約書の勉強会を開く際に、本書を参考書としてご利用いただけているとの声もいただいております。ありがとうございます。
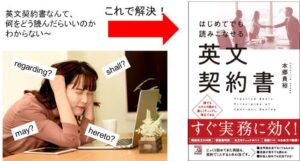
【私が勉強した原書(英語)の解説書】
残念ながら、EPC/建設契約についての日本語のよい解説書は出版されておりません。本当に勉強しようと思ったら、原書に頼るしかないのが現状です。
原書で勉強するのは大変だと思われるかもしれませんが、契約に関する知識だけでなく、英語の勉強にもなりますし、また、留学しなくても、英米法系の契約の考え方も自然と身につくという利点がありますので、取り組んでみる価値はあると思います。
| EPC/建設契約の解説書 | EPC/建設契約の解説書 | 納期延長・追加費用などのクレームレターの書き方 |
| 法学部出身ではない人に向けて、なるべく難解な単語を使わずに解説しようとしている本で、わかりやすいです。原書を初めて読む人はこの本からなら入りやすいと思います。 | 比較的高度な内容です。契約の専門家向けだと思います。使われている英単語も、左のものより難解なものが多いです。しかし、その分、内容は左の本よりも充実しています。左の本を読みこなした後で取り組んでみてはいかがでしょうか。 | 具体例(オーナーが仕様変更を求めるケース)を用いて、どのようにレターを書くべきか、どのような点に注意するべきかを学ぶことができます。実際にクレームレターを書くようになる前に、一度目を通しておくと、実務に入りやすくなると思います。 |
 |
 |
 |
| 納期延長・追加費用のクレームを行うためのDelay Analysisについて解説書 | 海外(主に米国と英国)の建設契約に関する紛争案件における裁判例の解説書 | 英国におけるDelay Analysisに関する指針 |
| クリティカル・パス、フロート、同時遅延の扱いに加え、複数のDelay Analysisの手法について例を用いて解説しています。 | 実例が200件掲載されています。実務でどのような判断が下されているのかがわかるので、勉強になります。 | 法律ではありません。英国で指針とされているものの解説です。この指針の内容は、様々な解説書で引用されていますので、一定の影響力をこの業界に及ぼしていると思われます。 |
 |
 |
Society of Construction Law Delay and Disruption Protocol
2nd edition February 2017 |