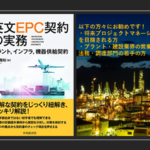私がEPC契約で真っ先に確認する点②
前回の復習
前回は、EPC契約におけるオーナーがコントラクターに支払う対価の調達方法毎にコントラクターが何を注意しなければならないかについての説明でした。
念のため、もう一度下に記載します。
① オーナーが第三者から融資を受けて、そこからコントラクターに対価を支払おうとしている場合:
オーナーと第三者間の融資契約における融資金額がEPC契約の対価をカバーしていることを確認の上、その融資契約の締結をEPC契約の発効条件とし、融資契約が締結されるまでは、コントラクターは何らの作業も開始する義務はなく、納期も起算されないようにする。
② オーナーの自己資金でコントラクターに対価を支払おうとしている場合:
EPC契約の対価に相当する金額についてLCを開設させる。そしてこのLCをEPC契約の発効条件とする。
オーナーが上記を拒否したら?
では、オーナーが上記のような手当てをすることを拒否した場合はどうするべきでしょうか。
例えば、「これを拒否するようなオーナーとは、EPC契約を締結してはいけない」とまで考えるべきでしょうか。
私は、EPC契約においては特に、このオーナーの資金力が十分かどうかという点は非常に重要であると考えます。
コントラクターが一生懸命仕事をしたのに、オーナーに払えるだけのお金がない、ということになると、コントラクターは無駄なことを、しかもお金をかけて行ったということになります。
この場合、利益を得られないだけではなく、それどころか、損失を被ることにもなってしまいます。
ここで、オーナーが、何らかの事情で上記のような手当てをEPC契約で定めることを拒むのであれば、以下のような方法もあると思います。
| オーナーは、EPC契約締結後すみやかにコントラクターに対して前払金を支払う。
その後、コントラクターが、前払金に相当するだけの仕事を遂行したら、その時点で進捗払いをしてもらう。
その次に、その進捗払い金に相当するだけの仕事をしたら、その時点でまた進捗払いをしてもらう。
これを繰り返す。
つまり、常にオーナーは、コントラクターが行う仕事に相当する分の対価を事前にコントラクターに支払う仕組みとする。
前払金の支払い、そして、その後の進捗払いをオーナーが怠ったら、コントラクターは作業を中断することができる。この中断によってコントラクターに追加で生じた費用はオーナーが負担するものとし、この中断によって工程に影響が出る分だけ納期は延長される。
さらに、その中断が一定期間継続したら、コントラクターは契約を解除することができ、コントラクターはそれまでに製造した機器についてオーナーに引き渡せば、解除までにオーナーから受領した対価をオーナーに返還する義務はない。 |
このようにしておけば、コントラクターはオーナーから支払ってもらった分だけ仕事を進めることになるので、「仕事をしたのに対価を得られない」、「対価をとりっぱぐれる」、というようなことが起きるリスクを減らすことができると思います。
この他にも、対価を得られないリスクを減らす方法はあるかもしれませんので、必ずしも上記でないといけないわけではありません。重要なのは、「プラントを建設してほしいとオーナーが言っているんだから、お金はあるはず。対価を支払わない、支払えない、なんていうことを途中で言ってくるはずがない」という前提をもつべきではなく、何らかの手当てをするべき、ということです。
要注意ケース
例えば、次のような場合には特に要注意です。
・オーナーそれ自体はたいしてお金を持っていない。しかし、オーナーの親会社はその国で有名な企業である。「オーナーが支払えなくても、親会社が最後はなんとかしてくれるだろう」と考え、オーナーの親会社から何らの保証も取らずにオーナーとEPC契約を締結してしまうこと。
・オーナーは、自分自身はさほど資金を持っていないが、銀行から融資を受ける予定である。銀行は、必ず融資すると言っている。しかし、融資契約の締結時期は、銀行内の手続きが現在他の案件で滞っているので、数カ月先になる見通しである。しかし、今すぐにでもEPC契約を締結し、作業を開始してもらいたいとオーナーが強く求めている。過去、その銀行が融資をすると言っておきながら実際にしなかった例は一度もない。
EPC契約に限らず、あらゆる案件で自社が対価を適切に得られるようにすることは最重要課題であるはずです。
しかし、EPC契約のように巨額の契約金額の案件の受注を目の前にすると、「案件の成功=契約受注」と考えてしまい、客先の資金調達力の有無への注意を怠ってしまう、ということも起きてしまうかもしれません。
「案件の成功」とは、「受注すること」ではないですよね。
受注した末に、無事に、予定通りの利益を得ることができて初めて、「案件の成功」と呼べるのではないでしょうか。
そしてその大前提となるのは、「コントラクターの直接の契約相手であるオーナーがコントラクターの対して払えるだけの資金を持っていること、または調達することができること」です。
ぜひこの点を特に忘れずに検討し、何かしらの手当てをしていただければと思います。
これでEPC契約をチェックする優先順位がわかる!
この記事をご覧になった方は、以下もお勧めです。
「EPCコントラクターからみたプロジェクトファイナンス」
『英文EPC契約の実務』は、お陰様で出版から6度の増刷となっております。
この本は、
・重要事項についての英語の例文が多数掲載!
・難解な英文には、どこが主語でどこが動詞なのかなどがわかるように構造図がある!
・もちろん、解説もこのブログの記事よりも詳しい!
・EPCコントラクターが最も避けたい「コストオーバーランの原因と対策」について、日系企業が落ちいた事例を用いて解説!
・英文契約書の基本的な表現と型も併せて身につけることができる!
ぜひ、以下でEPC契約をマスターしましょう!
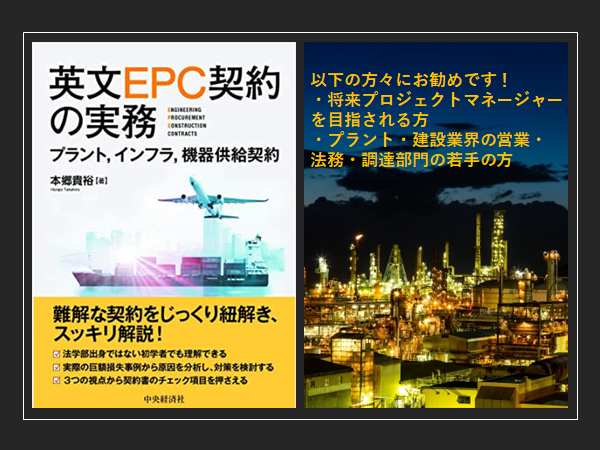
EPC契約のポイントの目次
【私が勉強した原書(英語)の解説書】
残念ながら、EPC/建設契約についての日本語のよい解説書は出版されておりません。本当に勉強しようと思ったら、原書に頼るしかないのが現状です。
原書で勉強するのは大変だと思われるかもしれませんが、契約に関する知識だけでなく、英語の勉強にもなりますし、また、留学しなくても、英米法系の契約の考え方も自然と身につくという利点がありますので、取り組んでみる価値はあると思います。
| EPC/建設契約の解説書 | EPC/建設契約の解説書 | 納期延長・追加費用などのクレームレターの書き方 |
| 法学部出身ではない人に向けて、なるべく難解な単語を使わずに解説しようとしている本で、わかりやすいです。原書を初めて読む人はこの本からなら入りやすいと思います。 | 比較的高度な内容です。契約の専門家向けだと思います。使われている英単語も、左のものより難解なものが多いです。しかし、その分、内容は左の本よりも充実しています。左の本を読みこなした後で取り組んでみてはいかがでしょうか。 | 具体例(オーナーが仕様変更を求めるケース)を用いて、どのようにレターを書くべきか、どのような点に注意するべきかを学ぶことができます。実際にクレームレターを書くようになる前に、一度目を通しておくと、実務に入りやすくなると思います。 |
 |
 |
 |
| 納期延長・追加費用のクレームを行うためのDelay Analysisについて解説書 | 海外(主に米国と英国)の建設契約に関する紛争案件における裁判例の解説書 | 英国におけるDelay Analysisに関する指針 |
| クリティカル・パス、フロート、同時遅延の扱いに加え、複数のDelay Analysisの手法について例を用いて解説しています。 | 実例が200件掲載されています。実務でどのような判断が下されているのかがわかるので、勉強になります。 | 法律ではありません。英国で指針とされているものの解説です。この指針の内容は、様々な解説書で引用されていますので、一定の影響力をこの業界に及ぼしていると思われます。 |
 |
 |
Society of Construction Law Delay and Disruption Protocol
2nd edition February 2017 |