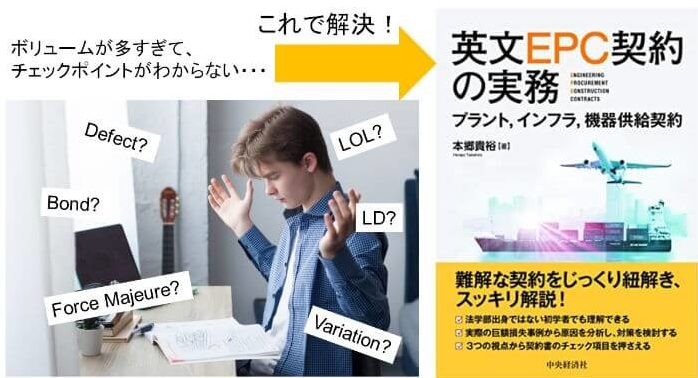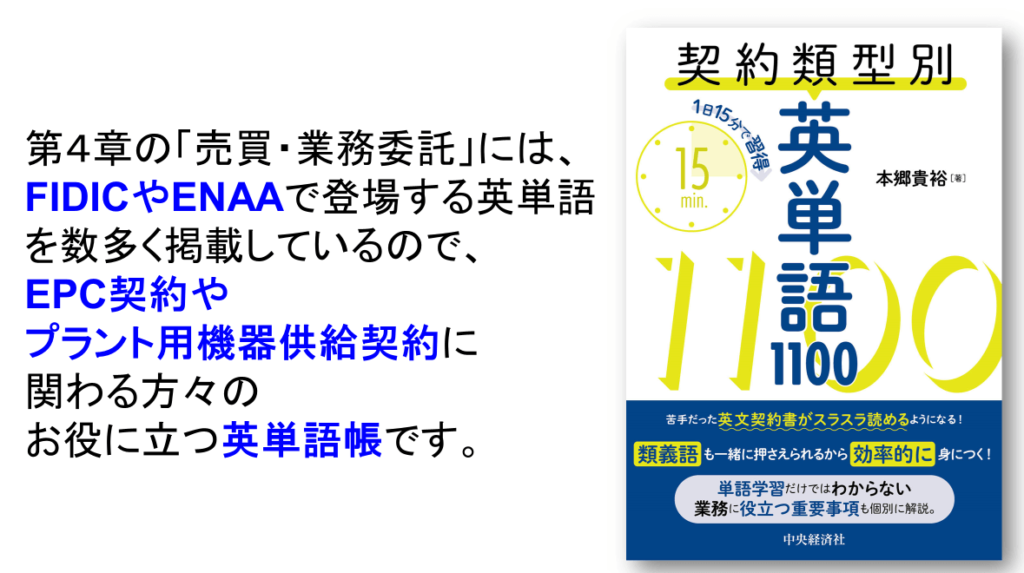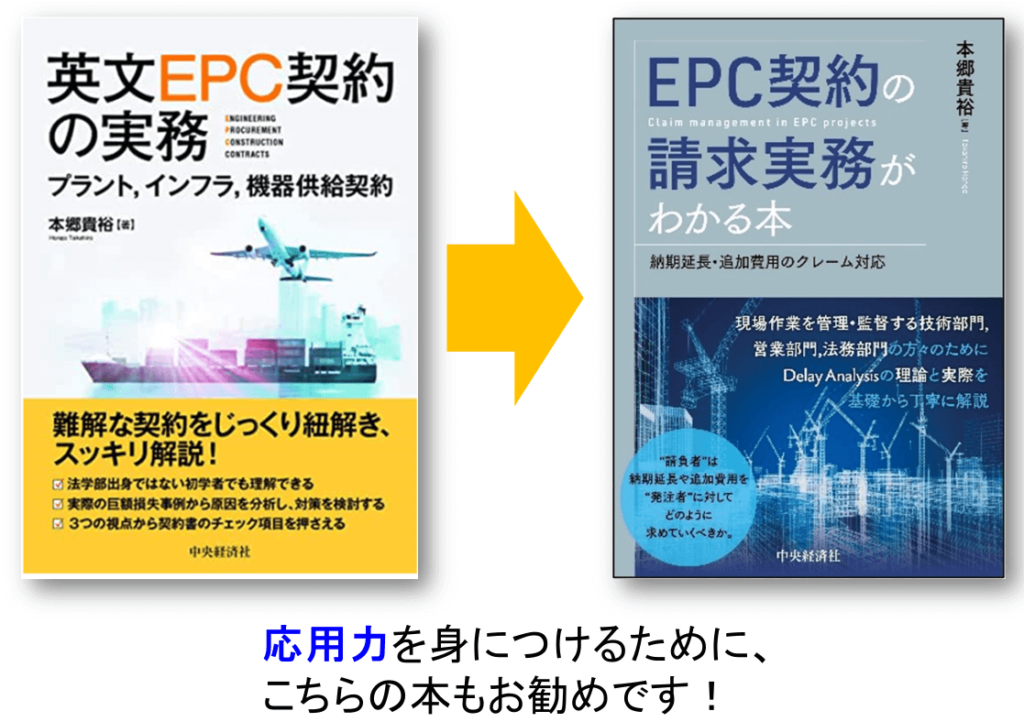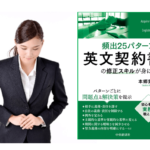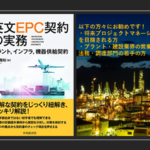契約書によく出てくる納期遅延LDとその算定方法を学ぼう!
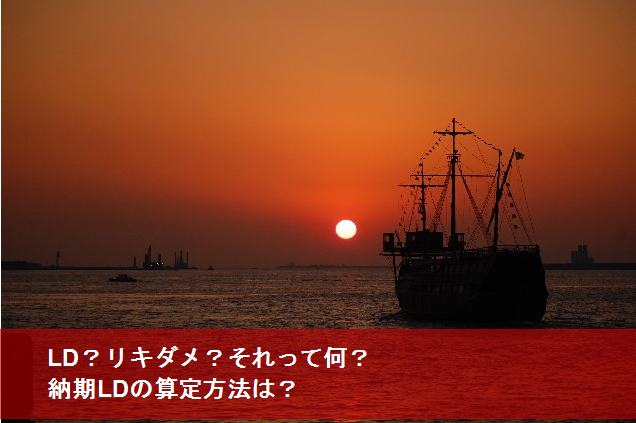
LD・リキダメとは何か?
コントラクターの原因で決められた納期にプラントを完成させることができなかった。
この場合、コントラクターは、オーナーに対して損害を賠償しなければならなくなります。
通常、損害賠償は、損害を被った者が、「これだけの損害を被りました!」ということを証明しなければなりません。つまり、オーナーが損害額を証明するのです。
しかし、EPC契約では、オーナーは、被った損害額を証明する必要はない、とされている場合が多いです。
それは、liquidated damagesというものを定めているからです。
これは、LDと省略して書き、「エルディー」とか、「リキダメ」などと呼ばれます。
![]()
日本の法律上、このLDに該当するのは、「予定された損害賠償金額」と呼ばれるものです。
(LDについては、こちらの動画でも解説しております!)
民法第420条に定められています。
これは、損害賠償金額を予め当事者間で合意したものです。
実際に生じた損害額を契約違反の後に算定しようとしても著しく難しい場合に採用されます。
EPC契約においてこのLDが採用されるケースが多いのは、プラントの完成が遅れた場合にオーナーが実際に被る損害を算定するのが難しいからです。
そして、EPC契約では、プラントの完成が1日遅れるといくらの損害賠償金額となるかが定められているものが多いです。すると10日遅れるとその10倍、30日遅れるとその30倍、というように、損害賠償額が決まります。
![]()
オーナーは、単に、納期に何日遅れたのかを示すだけでよく、実際にどれだけの損害額が生じたのかを証明する必要はないのです。
こうしてみると、このLDは、オーナーにとってとても有利な制度に思えますね。
ただ、日本の民法の定めに従うと、このLDを契約書に定めると、実際に生じた損害がこのLDより多くても、少なくても、裁判所ですら、LDとして定めた金額とは異なる金額を損害賠償として支払うようにコントラクターに求めることはできなくなります。これは、他の国の法律の下でもそうなのかどうかはわかりません。そのためか、EPC契約書にこの点が明記されていることが多いです。
補足(2016年11月16日)
もっとも、日本で損害賠償額の予定について争われたいくつかの裁判では、当事者間で合意されていた損害賠償額の予定の金額が、実際の損害とあまりにかけ離れている場合には、裁判所が実際の損害額を払えばよい、と判断しているものもあります。
よって、日本に限定していえば、仮にコントラクターが納期に遅れても、コントラクター側でオーナーが実際に被った損害を算定し、それが納期LDの金額よりも低い場合には、判例を根拠にしてオーナーと交渉するべきだと思います。また、海外の案件であっても、現地の法律事務所に相談して、納期LDの支払い金額を減額できるとする判例がないか相談してみてはいかがでしょうか。
納期LDの算定方法は?
では、この1日遅れた場合の損害賠償金額は、どのように決められるのでしょうか?
そもそも、実際に納期に遅延した場合の損害額を証明することができないからという理由でこのLDを採用しているので、「1日遅れたらいくらの損害賠償金額とする」というのを決めるのも難しそうに思えますよね。
そのため、「前の契約の時はいくらとしたから、今回も同じでよいだろう」という感じで決めてしまうことも多いのではないでしょうか。
この点、納期遅延のLDを契約に定める場合には、「納期に遅れると、オーナーはいかなる損害を被るか?」を実質的に考えることが重要になります。
この点、納期に遅れるということは、プラントの運転開始が遅れるということです。
プラントの運転開始が遅れると、オーナーがプラントの運転から得られるはずだった利益を得られなくなります。
ここで、オーナーはEPC契約の対価を、銀行などの金融機関から融資を受けている場合が多いです。というのも、EPC契約の対価は莫大な金額であることが多く、自己資金だけで賄うことは難しいためです。
オーナーはその融資分を返済する義務を負っているのですが、プラントの運転開始が遅れると、プラントの運転から得られる利益を得るのが遅れます。その分、返済するだけの資金を得るのも遅れます。その結果、返済が遅れるでしょう。
そうすると、返済が遅れたことによる遅延利息が生じます。
これが、納期遅延によってオーナーが被る損害の代表的なものです。
建設中に生じる利息なので、「建中利息」と呼ばれます。
英語では、interest during constructionですので、頭文字だけとって略して、「IDC」とも呼ばれます。
よって、この返済遅延によって生じる建中利息を基準にして、納期遅延のLDの金額を検討するというのが一つの方法だと思います。
もしも、オーナーが提示する納期遅延のLDの金額が、この建中利息よりもはるかに大きい場合には、「それは実際にオーナーが被る損害よりも高すぎる」として、より小さい金額に修正を申し入れるべきだと思います。
これであなたもLDマスターになれる!
納期遅延の場合のコントラクターの責任④ sole and exclusive remedy
EPC契約の責任関係をもっと知りたい方はこちら!
海外インフラ系の事業の英文契約書の頻出用語を知りたい方はこちら!
『英文EPC契約の実務』は、お陰様で出版から6度の増刷となっております。
この本は、
・重要事項についての英語の例文が多数掲載!
・難解な英文には、どこが主語でどこが動詞なのかなどがわかるように構造図がある!
・もちろん、解説もこのブログの記事よりも詳しい!
・EPCコントラクターが最も避けたい「コストオーバーランの原因と対策」について、日系企業が落ちいた事例を用いて解説!
・英文契約書の基本的な表現と型も併せて身につけることができる!
ぜひ、以下でEPC契約をマスターしましょう!
EPC契約のポイントの目次