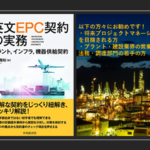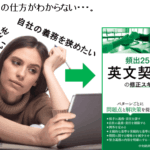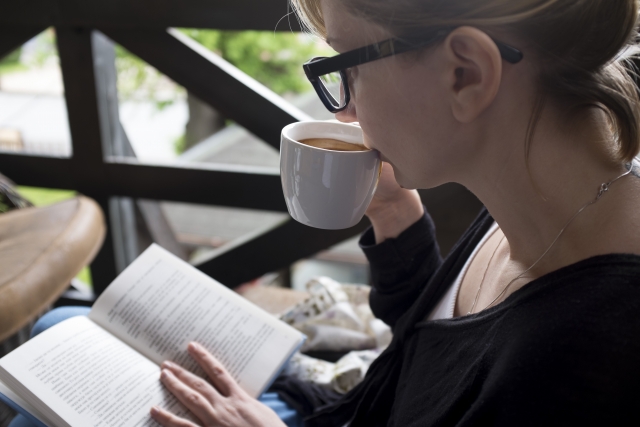英文契約で「権利」(right/entitlement)を定める方法

前回は、「義務を定める方法」について解説しました。
今回は、「権利を定める方法」を紹介します。
契約書に主に定められているのは、契約当事者間の権利・義務・責任関係なので、この表現も義務と同じくらい重要ですので、しっかりマスターしましょう!
権利を表す表現には、以下のようなものがあります。
・may
・is entitled to do
・has the right to do
・is allowed to do
なお、is entitled to+名詞でも権利を表すことができます。
権利は、「~することができる」という意味なので、中学校で習ったcanを用いたくなるかもしれません。
しかし、英文契約では、canは「物理的・精神的にに何かをする能力がある」ということを表す際に使われ、権利を表す場合には使われないのが通常なので注意しましょう。
ここで、権利と義務の関係について確認しておきましょう。
権利と義務は、表裏一体の関係にあります。
例えば、売買契約において、売主が製品を買主に引き渡すことを条文として定める場合、次のように2つの書き方があります。
| ① The Seller shall deliver the Product to the Purchaser.
「売主は、製品を買主に引き渡さなければならない」 ② The Purchaser may require the Seller to deliver the Product to the Purchaser. 「買主は、製品を買主に引渡すように売主に対して求めることができる」 |
つまり、①は売主の義務として、反対に②は買主の権利として書いています。
また、対価の支払いに関しても、同じように2つの書き方があります。
| ① The Purchaser shall pay the Contract Price to the Seller.
「買主は、売主に対して、契約金額を支払わなければならない。」 ② The Seller is entitled to payment of the Contract Price. 「売主は、契約金額の支払を得る権利がある。」 |
どちらで書いても法的な効果に違いはありません。
そして、両方を書く必要はなく、権利か義務のどちらかで定めれば足ります。
ただ、一般的には、義務の形である①で定められることが多いです。
よって、相手に何かして欲しいことがあり、それを契約書に定める場合には、まずは①のように義務の形で書くことを検討してみましょう。
ちなみに、権利の形で書かれるのが普通とされているものとしては、次のようなものがあります。
| The Contractor may suspend performance of all of the obligations under this Agreement.
請負者は、本契約に基づく義務のすべての履行を中断することができる。 The Purchaser is entitled to terminate this Contract. 買主は、本契約を解除することができる。 |
suspend ~を中断する terminate ~を解除する
役に立つ英文契約ライティング講座
| ①義務を定める方法 | ④shall be required to doとshall be obliged to doの問題点 | ⑦義務違反の場合を表す方法 | |
| ②権利を定める方法 | ⑤英文契約の条文は能動態で書くとシンプルかつ分かりやすい英文になる! | ||
| ➂shall be entitled to doとshall be required to do | ⑥第三者に行為をさせるための書き方 |
上記は、本郷塾の5冊目の著書『頻出25パターンで英文契約書の修正スキルが身につく』の8~11頁部分です。
英文契約書の修正は、次の3パターンに分類されます。
①権利・義務・責任・保証を追記する→本来定められているべき事項が定められていない場合に、それらを追記する。
②義務・責任を制限する、除く、緩和する→自社に課せられている義務や責任が重くなりすぎないようにする。
➂不明確な文言を明確にする→文言の意味が曖昧だと争いになる。それを避けるには、明確にすればいい!
この3つのパータンをより詳細に分類し、頻出する25パータンについて解説したのが本書です。
そして、今お読みいただいたのは、パターン②の「権利を定める方法」に該当するものです。
本書の詳細は、こちらでご確認できます。
英文契約書をなんとか読めても、自信をもって修正できる人は少ないです。
ぜひ、本書で修正スキルを身につけましょう!きっと、一生モノの力になるはずです!
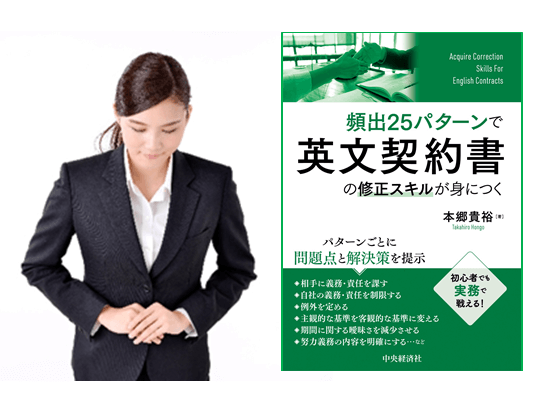
本郷塾で学ぶ英文契約のyoutubeチャンネルのお知らせ
「本郷塾で学ぶ英文契約」のyoutube動画では、英文契約の重要単語について動画で解説しております。
2024年1月から始めたばかりですが、最低でも週一で更新していきますので、ぜひ、ご覧ください。