英文契約で相手の「義務」(obligation/duty)を定める方法
~役に立つ英文契約ライティング講座①~
作為義務:「~しなければならない」
契約書の修正で最も基本的なものは、「相手に新たな義務を課す」ことです。
そこでまず、「契約当事者は・・・する義務がある」または「契約当事者は・・・しなければならない」という意味の表現を覚えましょう。
これには、以下のようなものがあります。
①shall
②is required to
➂is obliged to
④agrees to
上の4つの中で、義務を表す際にもっともよく使われるのは、shallです。
この点、「~しなければならない」はmustである、と習ってきたと思いますが、英文契約書では通常、契約当事者の義務を表す際にmustは使われない点に注意しましょう。
2つめのbe required to doは直訳すると「~することを求められている」となりますが、これでshallと同じく、義務を表します。
4つ目のagree to doは「~することに同意する」という意味ですが、ある行為を行うことに同意するということは、契約上は、その行為をすることが義務となる、ということになります。
もっとも、義務を表すためにagreeを使うのはおかしいとも言われています。
というのも、英文契約書は、本文に入る前の頭書と呼ばれる部分で、次のような表現があるからです。
| ・・・the parties hereto agree as follows:
本契約の当事者は、以下の様に合意する。 |
the parties hereto=the parties to this Agreement 本契約の当事者
as follows:以下の様に
この後に、契約当事者の義務が記載されていきます。
その際に、例えば、次のような条文が定められていたら、「両当事者は、売主が合意することについて合意する」となり、不自然ですよね。
| ・・・the parties hereto agree as follows:
・・・ The Seller agrees to deliver the Product to the Purchaser before the Deadline for Delivery. 売主は、納期までに製品を買主に引き渡すことに合意する。 |
deliver ~を引渡す delivery 引渡し deadline 期限
よって、当事者の義務を表す場合に、上で紹介した4つの中でagree to doはあまり使わないほうがよいといわれています。
上の例文でいえば、次のように書くのが自然です。
| The Seller shall deliver the Product to the Purchaser by the Deadline for Delivery.
売主は、納期までに製品を買主に引き渡さなければならない。 |
また、次のような条文が定められていることもあります。
| ・・・the parties hereto agree as follows:
・・・ The Parties agree that the Seller shall deliver the Product to the Purchaser before the Deadline for Delivery. 契約当事者は、売主が、納期までに製品を買主に引き渡さなければならないことに合意する。 |
この例文では、下線部分は明らかに不要です。
上に示したように、英文契約の頭書には、「契約当事者は、以下の様に合意する」と記載されているので、本文中で重ねて「契約当事者は~と合意する」という記載は二重に定めていることになるので、不要です。
不作為義務・禁止:「~してはいけない」
上で紹介した表現は、ある行為を積極的に行うように契約当事者に義務付けるものでした。
これを作為義務といいます。
一方、ある行為を行わないように契約当事者に義務付ける、つまり、「~してはいけない」というように、ある行為を禁止する場合もあります。
これを不作為義務といいます。
これは、次のように書きます。
契約当事者+shall not+動詞の原形
この不作為義務を書く際に注意したいのが、be not required toやbe not obliged to doとは書かない点です。
ここで、「義務を表す際にはbe required toやbe obliged toを使えるのだから、それを否定するbe not required toやbe not obliged toは不作為義務を表すのでは?」と思った読者の方もいるかもしれません。
しかし、その理解が誤りです。
下の例文を見てください。
| The Receiving Party shall not disclose the Confidential Information to any third party. |
receive ~を受領する disclose ~を開示する confidential information 秘密情報
これは、「受領当事者は、秘密情報を第三者に開示してはならない」という意味です。
一方、be not required toを用いた次の英文はどうでしょうか。
| The Receiving Party is not required to disclose the Confidential Information to any third party. |
これは、「売主は、秘密情報を第三者に開示することが求められていない=開示する義務はない」となります。
つまり、売主は、秘密情報を開示しなくてもよいが、開示してもよい、という意味になってしまうのです。
これはis not obliged toを用いた場合も同じです。
これでは、「開示してはならない」という「禁止」の意味が全く表されていないことになります。
よって、「~してはならない」という禁止・不作為義務を表す際は、shall notを使わなければならず、be not require to doやbe not obliged to doを使ってはならないのです。
次回は、「自社の権利を定める方法」について解説します!
役に立つ英文契約ライティング講座
| ①義務を定める方法 | ④shall be required to doとshall be obliged to doの問題点 | ⑦義務違反の場合を表す方法 | |
| ②権利を定める方法 | ⑤英文契約の条文は能動態で書くとシンプルかつ分かりやすい英文になる! | ||
| ➂shall be entitled to doとshall be required to do | ⑥第三者に行為をさせるための書き方 |
上記は、本郷塾の5冊目の著書『頻出25パターンで英文契約書の修正スキルが身につく』の2~5頁部分です。
英文契約書の修正は、次の3パターンに分類されます。
①権利・義務・責任・保証を追記する→本来定められているべき事項が定められていない場合に、それらを追記する。
②義務・責任を制限する、除く、緩和する→自社に課せられている義務や責任が重くなりすぎないようにする。
➂不明確な文言を明確にする→文言の意味が曖昧だと争いになる。それを避けるには、明確にすればいい!
この3つのパータンをより詳細に分類し、頻出する25パータンについて解説したのが本書です。
そして、今お読みいただいたのは、パターン①の「義務を定める方法」に該当するものです。
本書の詳細は、こちらでご確認できます。
英文契約書をなんとか読めても、自信をもって修正できる人は少ないです。
ぜひ、本書で修正スキルを身につけましょう!きっと、一生モノの力になるはずです!
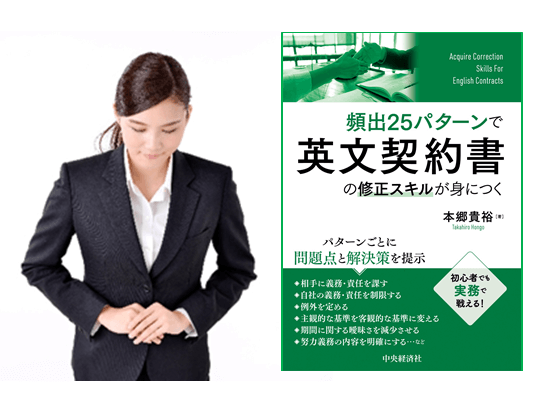
本郷塾で学ぶ英文契約のyoutubeチャンネルのお知らせ
「本郷塾で学ぶ英文契約」のyoutube動画では、英文契約の重要単語について動画で解説しております。
2024年1月から始めたばかりですが、最低でも週一で更新していきますので、ぜひ、ご覧ください。







