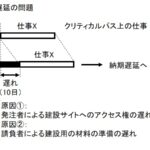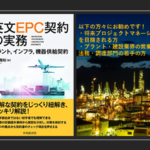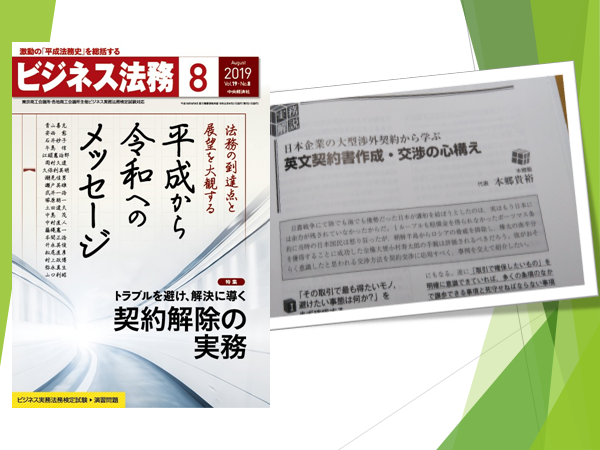初めて教育係(メンター)に選ばれた方へ①~もつべきマインドとは?~

新入社員が配属されて、もう大分経ちましたでしょうか。
このブログを読んでくださっている方の中には、自分の部門に配属された新入社員の教育係(以下、「メンター」)に選ばれ、日々新人を育てることに力を注いでいる方もいるのではないかと思います。
その中には、うまくやれている人もいれば、そうでもない人もいることでしょう。
特に初めてメンターになった方にとっては、色々な点で、こういうときはどう対応したらいいのか?と悩むこともあるかと思います。
私もメンターを何度か経験しました。メンターとしてではなくても、後輩と一緒に仕事をしたことも何度もあります。
その中で自分なりに色々と気付かされたこともありました。
そこで、今回は、メンターになって思ったことや後輩と仕事をして気付かされたこと等を書いてみたいと思います。
マインド
私は、何かに取り組む際には、どんなときも、それにどのように取り組むべきか、という心の持ち方、マインドが重要だと思っています。マインドが何もないままに取り組むと、漫然と取り組むことになります。マインドがないと、悩んだときにどのように進むべきかの指針がないことになり、その場その場の場当たり的な動き方しかできなくなります。
そのため、私は初めてメンターに選ばれたときに、それまで自分を育ててくれた先輩や上司の方々を参考にし、「メンターとはどうあるべきか」という点を自分なりに考え、以下の三つを必ず守ろうと決意しました。
・「メンターに選ばれたということは、自分は、部長候補に選ばれたということである」と思い込む
・自分がそれまでに到達したレベルに1年でも早く到達できるように導くように心がける
・他の誰を敵に回しても、後輩の味方になると決める
以下、一つずつ説明します。
「メンターに選ばれたということは、自分は、部長候補に選ばれたということである」と思い込む
これは真実なのでしょうか。
必ずしもそうではないでしょう。
もしかしたら、「新入社員の教育なんて面倒だ、誰か手の空いている人にまかせよう」といった非常に安易な理由で任された人もいるかもしれません。
毎年入ってくる新入社員のメンターは、それこそ大勢いるわけです。「メンターになったくらいで部長候補になったと言えるのであれば、一体この会社に部長候補は何人いるんだ?」ということになります。
しかし、真実がどうであるかは、この際関係ありません。
ある仕事をするとき、モチベーションをあげるために、「これはものすごく重要な仕事だ!」と自分に言い聞かせる、ということをしますよね。
それと同じです。
自分は、将来の会社の戦力を育て上げる重要な仕事を任されたと思い込みましょう。そうすれば、手は抜けなくなるはずです。
「適当でいいや、育とうが育たなかろうが、自分には関係ねー」なんて思えないはずです。
「自分の雑用係になってもらおう」とも思えないはずです。
「今日、俺は不機嫌だから、後輩を怒鳴りつけて自分の憂さ晴らしをしてやろう!怒鳴られるのに我慢するのは後輩の仕事だ」なんてことも、まず思えないはずです。
自分がそれまでに到達したレベルに1年でも早く到達できるように導くように心がける
これは、「会社は組織である」ということを考えれば自ずと生まれる考えではないでしょうか。
組織は常に成長しようとしています。
成長とは、より多くの利益を上げられるようになる、ということだと思いますが、数字だけが勝手に伸びていくわけがありません。数字は人の成長の結果ではないでしょうか。
特にこの点が重要になる理由は、優秀な新人のメンターになったときです。メンターと新人の年が割と近いと、メンターは新人の優秀さに気づいた時に、ある種の恐怖を抱くことになるかもしれません。それは、「自分が追い越されるかもしれない」という恐怖です。
そう感じると、中には、「あまり成長させないようにしよう」という考えも浮かぶかもしれません。
しかし、それは組織にとって非常にマイナスです。
「組織なんてカンケーねー!大事なのは自分のことだ!」
と思う方もいるかもしれません。しかし、その優秀な新人は、あなたがメンターである期間はあなたの妨害活動が功を奏して一時は伸び悩むかもしれませんが、あなたから解放された後でメキメキ実力を発揮し、その後あっさり追い抜いていく可能性が高いと思います。そうなったときに、昔の仕返しをされることになるような振る舞いは避けたほうがよいのではないでしょうか?
他の誰を敵に回しても、後輩の味方になると決める
新入社員の多くは、無力です。
会社に慣れた人からしてみれば当たり前のことも、新人には全くわからないものです。何が正しくて何が正しくないのかも驚くほどわからなかったりします。逆に言えば、それだけ会社は特殊な世界であるともいえると思います。「○○の常識、世間の非常識」なんて言葉があるくらいです。世間の常識を学生が知っていても、会社の常識を知らないなんてことは普通にあるでしょう。
そんな新入社員に会社の常識を教えることができるのは、まさにメンターではないでしょうか。
そして会社の常識は知らないが、それでもやる気のある新人であればあるほど、仕事では挑戦しようと思っていると思います。その結果、失敗することもあるでしょう。それが会社の常識を無視した失敗であれば、余計に怒られることになると思いますが、その時にメンターまで一緒になって、「オラー!何やってんだ!!(自分は悪くないもんね)」と周りと混ざって非難しまくったら、新人は一体どう思うでしょうか。
新人の味方になれるのは、メンターだけです。そういうときは、自分も一緒に怒られ、後で個室ででも、じっくり新人に会社の常識を教えるのがよいのではないでしょうか。
次のページ:初めて教育係(メンター)に選ばれた方へ②~実践するべきことは?~